 なおき
なおき介護職に就職・転職を考えているけど未経験でも大丈夫なの⁉なんて思ってしまいませんか?
『未経験だから不安』だという気持ちはよくわかります。
しかし、あなたが介護士を選択しないことで、生活の支えを必要とする高齢者が安心して暮らせなくなるかもしれません。
あなたが、介護士の道を選択したらどこかの誰かの生活を支える大切な存在となり、社会貢献できるでしょう。
未経験でも安心して下さい。あなたのやさしさと思いやりが、どんなものより力になります。
この記事は40代の介護士が「なぜ介護士を選択したのか」「どんなライフスタイルを送っているのか」を詳しく解説しています。
この記事を読んで介護の世界を少しでも知るきっかけになれば幸いです。
この記事の執筆者
特別養護老人ホーム 勤続20年
介護福祉士
副主任
認知症介護実践リーダー研修 履修済
40代の介護職が語る 気づけば介護士の道を歩んでいた
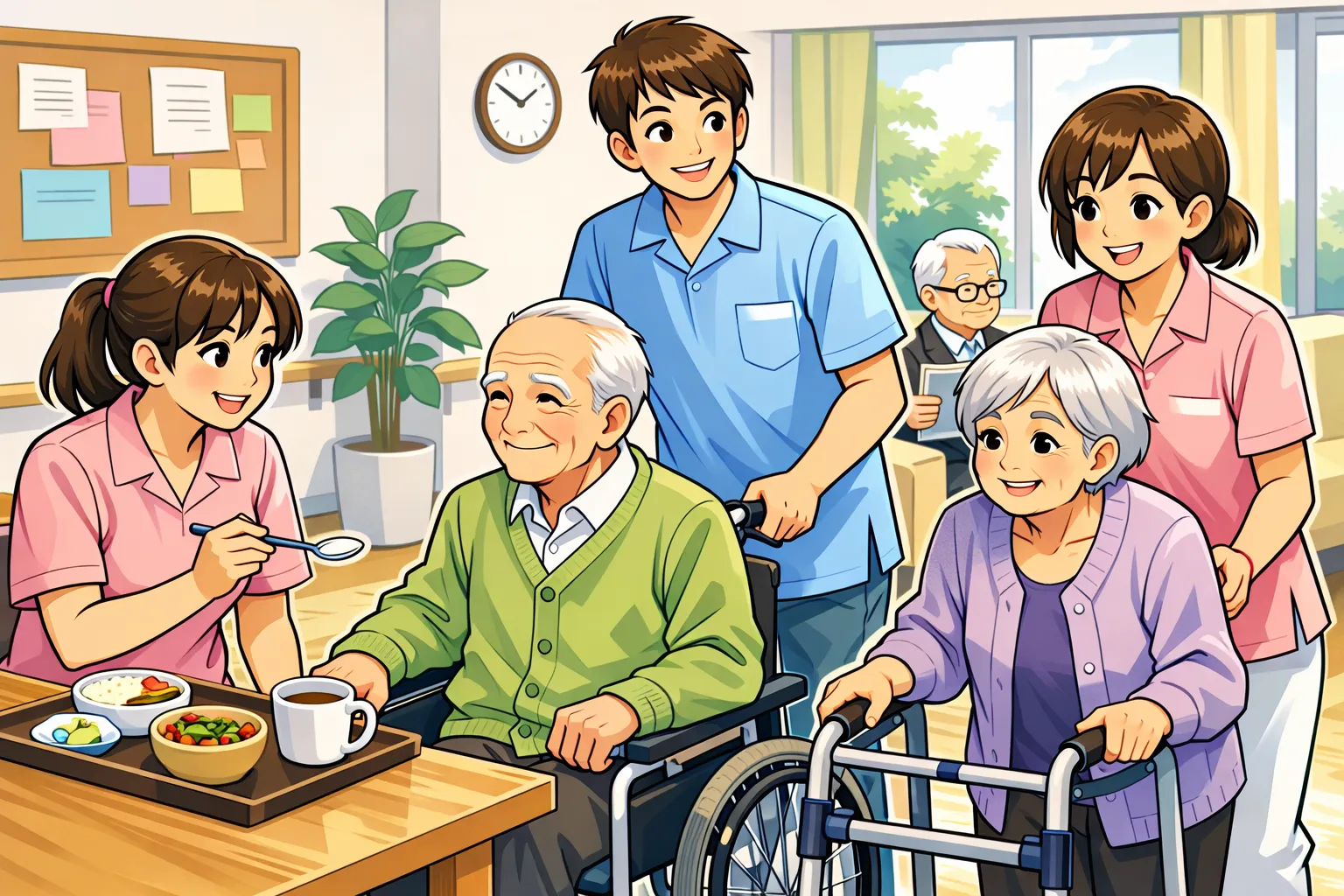
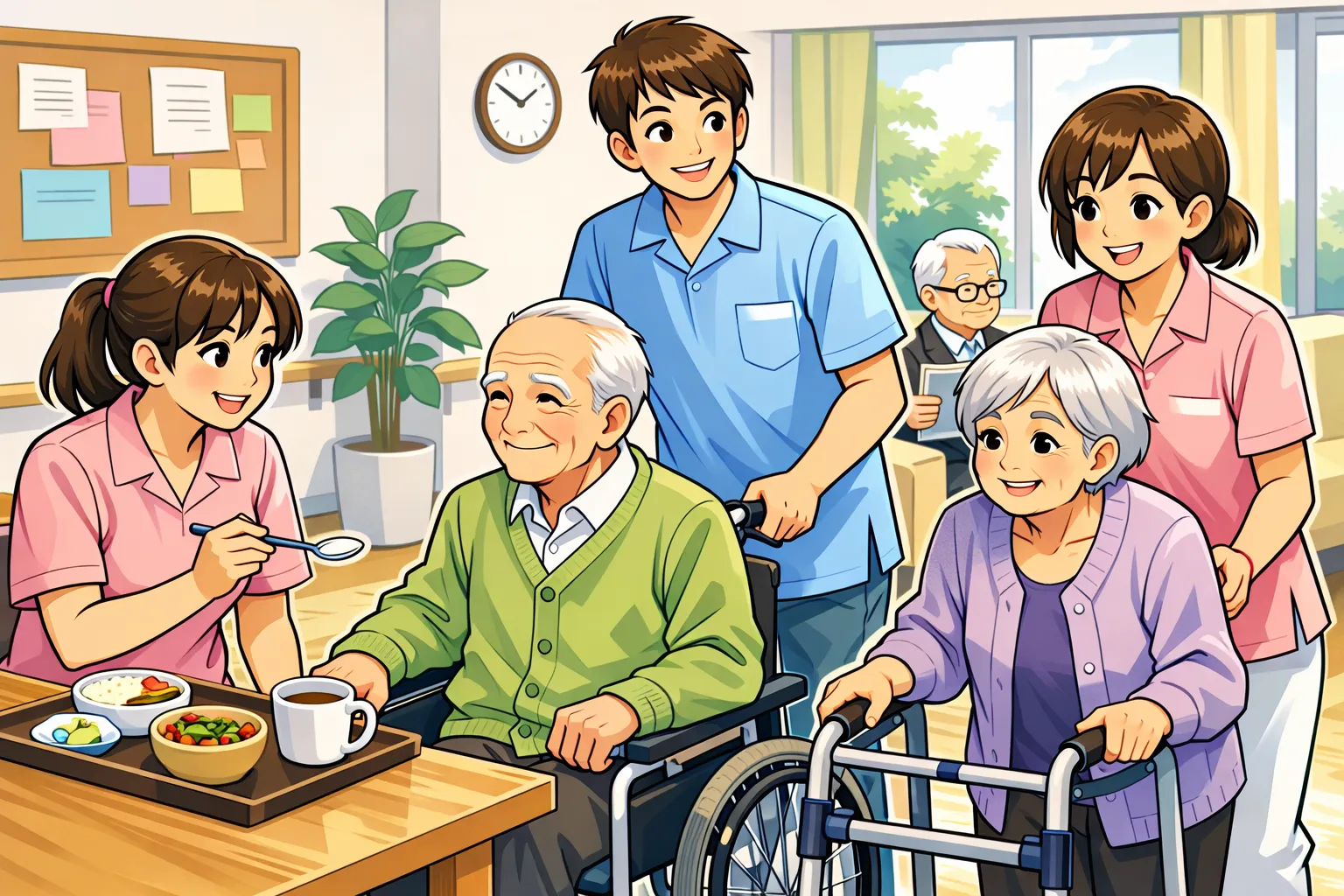
私が介護士を目指したのは、祖母が脳梗塞で身体が不自由になったことが大きなきっかけでした。
両親が共働きだったため、祖母と過ごす時間が長く、日常のちょっとしたお手伝いをするのが当たり前に。
さらに、デイサービスを利用していた祖母の送迎を間近で見ていたことで、介護という仕事がぐっと身近なものになりました。
「介護士になろう」と強く意識した瞬間があったわけではありません。気づけば自然と、この道を歩んでいたのだと思います。
祖母との時間が、私を介護士の道へ導いてくれた
祖母とともに過ごした時間が、私を介護士の道へ導いてくれたのだと思います。
私が介護士を目指した理由のひとつに、祖母の存在があります。
祖母は私が5歳のときに脳梗塞を発症し、右半身麻痺になりましたが、負けず嫌いな性格もあり、懸命にリハビリに励んだ結果、ほとんどのことを自分でこなせるようになりました。
とはいえ、家族としては心配も多く、私も自然と祖母の手伝いをするようになりました。そのお礼にお小遣いをもらうこともありましたが、私にとっては「手伝い」ではなく、ただ祖母と一緒に過ごす日常の一部でした。
両親は共働きで、平日は祖父母の家で過ごすことが多かったので、勉強や友達づくりまで率先してサポートしてくれる、優しくて頼もしい存在でした。
そんな日々を過ごす中、高校の通学バスで見かけた福祉学科のある大学の広告が妙に心に残り、気づけば進学先の第一候補になっていました。
学びよりも仲間。全力で楽しんだ大学生活
私の進学した大学は、開校してまだ3年目だったのでカリキュラムも手探りな状態の大学でした。
私の入った福祉心理学科は、福祉と心理学を学ぶ学科でしたが、肝心の介護技術を学ぶ授業がなく疑問をもったのを覚えています。
4年間で行った現場実習はデイサービスに2年生後半に14日間、3年生前半に14日間の短いものでした。
積極性はなく受け身だった私は、ただ現場の体験をするだけの内容の薄い実習でしたが、当時は早く終わって欲しいとだけ思ってしていました。
学問とは打って変わって、大学生活は、意気投合する仲間が多く、毎日勉強そっちのけで遊んでいました。
授業の内容は、右から左へ、居眠りしたり、さぼったりして、成績は覚えていませんがめっちゃ悪かったと思います。
お金をだしてくれた両親には、本当に申し訳のないことをしたと思っています。
でも、そのおかげというのも変ですが、今でも仲良く付き合っている友だちができました。
今でも、大学生活は人生で1番楽しかったと思います。
卒業論文は適当に終わらせ、最大のイベント社会福祉士の試験も落ち、大学生活は終わりました。
40代の介護職 消極的だった就活。でも、今の職場に出会えた


就職活動に本気で取り組んだ記憶はあまりなく、受けたのはたった2つの高齢者施設だけでした。
1つ目は、当時付き合っていた彼女と同じ法人で働きたいという不純な動機で受験しましたが、不合格。
特に強い志望動機があったわけでもなく、当然の結果だったのかもしれません。
その後もなかなか就活に本腰を入れられず、周りが次々と内定を決めていく中で、焦りを感じながら迎えた卒業間近の2月末。ようやく重い腰を上げ、応募した施設で採用が決まりました。
偶然のような流れで入職しましたが、気づけば今もこの職場で働き続けています。
人権を尊重しながら、より良い介護を模索する日々
介護の現場では、「人権尊重」という理念のもと、利用者様がこれまで大切にしてきたライフスタイルを尊重し、高齢者の方に、ふさわしい言葉遣いや態度を心がけながら支援しています。
しかし、長年働く中で、他の施設から来た職員の話を聞くたびに、自分たちの援助技術や知識がまだまだ不足しているのではないかと感じることがあります。
介護の経験を重ねる中で、援助に対する考え方も深まりました。 「この方にはどんな支援が必要か」「どうすれば自立を促せるのか」――利用者様の状態を観察し、コミュニケーションを重ねながら、その人に合った援助を提案できるようになったと実感しています。
そして、5年目を迎えた頃、気づけば現場のリーダーとして皆を引っ張る立場に。 最初は不思議な気持ちでしたが、これまでの経験が自信につながり、チームをまとめる役割にもやりがいを感じるようになりました。
介護はただの「お世話」ではなく、その人らしい生活を支える仕事。そう強く思うようになったのも、この頃からかもしれません。
感情を抑えた指導が求められる時代。それでも私たちは人間
私が新人だった頃は、先輩から厳しく指導を受けるのが当たり前の時代でした。
当時は、今でいうパワハラやモラハラの概念もほとんどなく、ハラスメントといえば「セクハラ」くらい。
現在は指導する立場になりましたが、ハラスメント対策の影響で、思ったことをストレートに伝えづらい環境になっています。とはいえ、指導の際に感情が入り、つい強く言ってしまうことも…。
適切な指導とハラスメントの境界線に悩みながらも、どうすれば後輩が成長できるのかを模索する日々です。



感情があるからこそ相手に響くこともあるよね
今の職場環境では、感情を抑え、淡々と指導することが求められています。
指導する側にとっては、言葉を選びながら慎重に伝えなければならない難しい時代になりました。
どの職場でも、「指導=ハラスメントにならないように」という空気があり、必要な指導すらためらうこともあるのではないでしょうか。
ですが、私たちはロボットではなく、感情を持った人間です。時には熱くなることもあれば、悩みながら伝えることもあります。
感情を押し殺すことなく、適切に指導できる環境をどう作るか。今、現場で働く私たちが考えるべき課題なのかもしれません。
成長を実感した瞬間。ボディメカニクスとの出会い
就職して1年、2年と経つにつれ、少しずつ介護技術や考え方が成長している実感がありました。
しかし、当初は先輩職員の動きを見よう見まねで覚えようとしていたものの、基本的な技術が身についていなかったため、なかなか上達せずにいました。
そんな中、3年目に経験豊富なパート職員から「ボディメカニクス」について教えてもらったことが大きな転機になりました。
「無理なく、効率的に身体を使うことが大切」その言葉を聞いてから、介助のコツがつかめるようになり、自分でも技術が向上しているのを実感できるようになりました。
学ぶべき基礎を理解することで、介護はただの力仕事ではなく、理論に基づいた技術なのだと気づいた瞬間でした。



全ての介護技術につながる財産をゲット!!
特養介護職のリアル。休みが不規則でも楽しみ方は無限大!
特養の介護職員はシフト制。土日・祝日が必ず休みとは限らず、お盆やお正月に働くことも珍しくありません。
そんな時、世間が休日を楽しんでいるのを見て「うらやましい…」と感じることもあります。
でも、実は平日休みには大きなメリットがあるんです!
どこへ行っても空いている、道路が渋滞しない、人気スポットも並ばずに楽しめる。 これって、かなり贅沢な時間の使い方だと思いませんか?
しかも、私の周りには同じ介護職の友人も多く、予定が合わせやすい。 人混みや渋滞のストレスとは無縁で、快適に出かけられるのでノンストレスで楽しめます。
職場の人間関係は良好ですが、やはり大勢の人が集まると色々な出来事があり、ストレスを感じることも。
そんな時こそ、旅行やドライブ、温泉、季節のレジャーで「非日常」に身を置き、心をリフレッシュ!
介護職の休みは不規則だけど、だからこそ味わえる特別な楽しみ方があるんです。
40代の介護職 今やるべき事
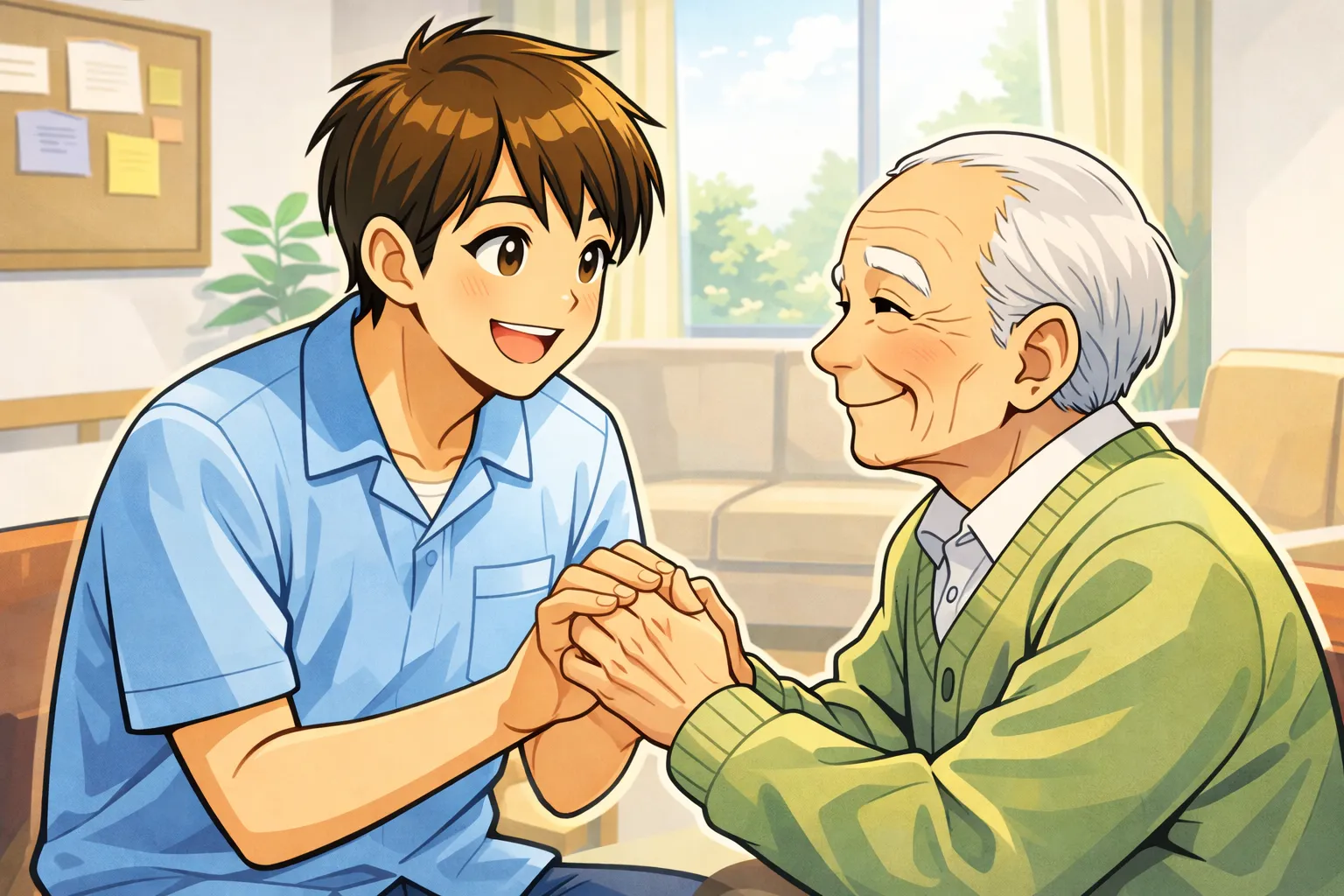
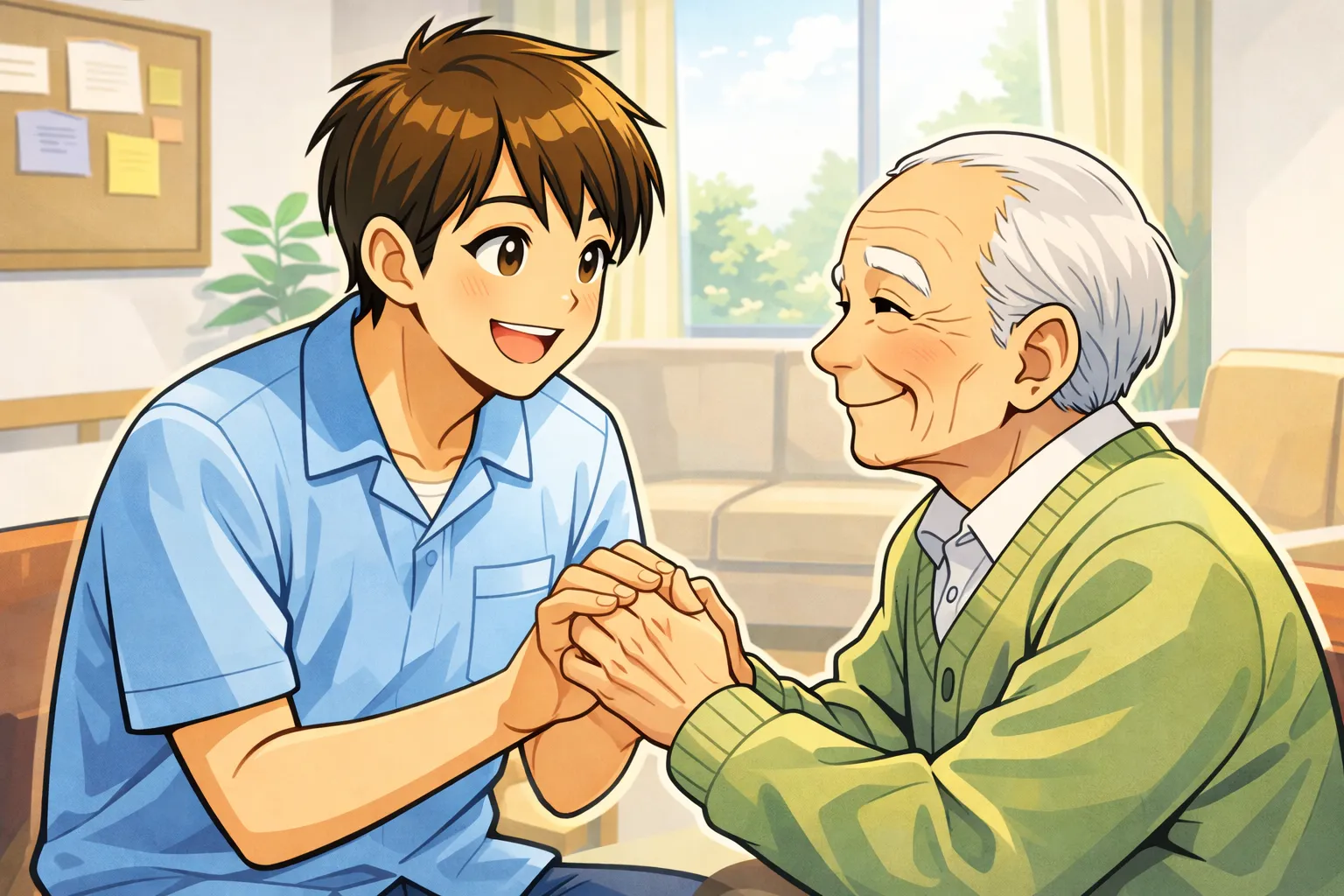
介護の現場で20年間働いてきた私が、今強く感じていること。それは、周りの職員の介護スキルを向上させることだと思っています。
近年、職員の質の低下が目立ち、利用者への援助が十分に行き届いていない場面が増えていると感じます。しかし、指導の際にはハラスメントにならないよう細心の注意を払わなければならず、注意や指導をためらってしまうことも事実です。
間違った介護を続けていると、自分のミスに気づくことすらできません。 それが放置されれば、介護の質はどんどん低下し、最終的に利用者が不利益を被ることになります。
20年前、私は厳しい指導を受けながら成長しました。今でも心に残っているのは、指導の厳しさではなく、そこに込められた「本気の想い」です。しかし、現代ではその方法では通用しません。AIのように感情を排除した指導がいいのでしょうか?
確かに、感情的な言葉は「怒られた」という印象だけが残り、肝心の指導内容が伝わりづらくなってしまうこともあります。しかし、相手の心を動かすのもまた感情です。 感情を押し殺すのではなく、適切に伝え、職員と信頼関係を築くことが重要だと考えます。



感情コントロールは難しいですよね
結局のところ、ハラスメントを避けるために最も大切なのは、日頃からの職員とのコミュニケーションだと感じています。普段から信頼関係が築けていれば、指導がパワハラとして受け取られることは少なくなります。(もちろん、伝え方には十分注意が必要ですが。)
これから私がやるべきことは、職員としっかりコミュニケーションをとり、安心して指導ができる環境を整えること。 そして、ただマニュアル的に教えるのではなく、「相手の心を動かす指導法」を追求していくことです。
これからの介護現場を支えるために、時代に合った指導を考え、より良いケアを提供できるチームを作っていきたいと思います。


コメント
コメント一覧 (1件)
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。